FEATURES東京個別チャンネル
FEATURES一覧に戻る2019年7月31日、NASA(アメリカ航空宇宙局)が探査衛星「TESS」の観測によって、地球から31光年の距離に3つの惑星を持つ惑星系を発見したと報じました。(※1)そのうちの一つの惑星は生命が存在する可能性があるハビタブルゾーンに属することがわかりました。今回は「TESS」と「TESS」が発見したハビタブルゾーンに属するGJ357dについて詳しく説明します。
1.探査衛星TESSが発見した惑星とは
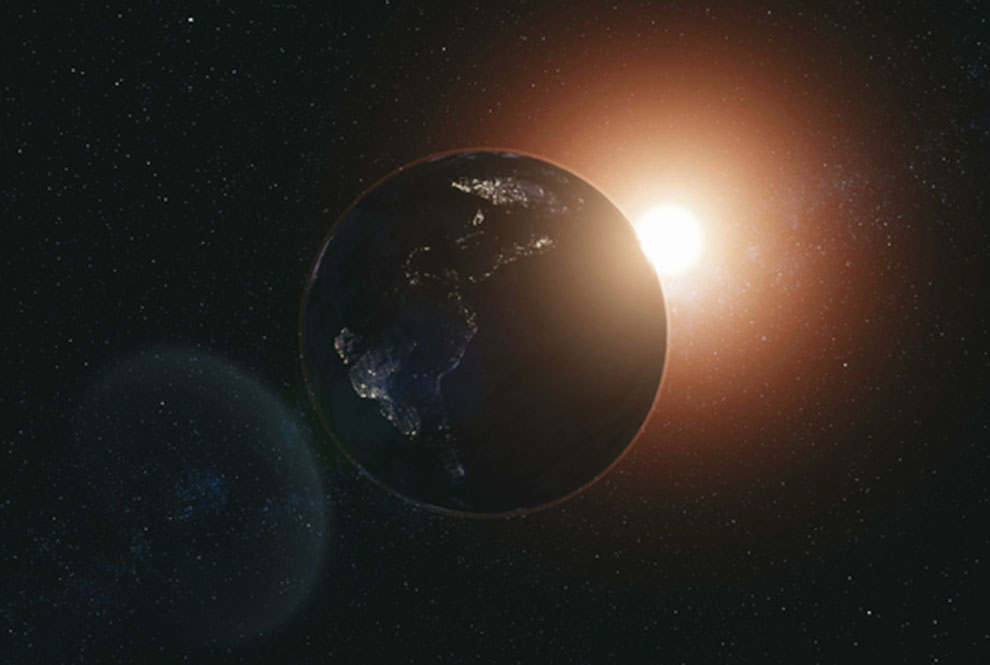
2018年4月19日に打ち上げた(※2)探査衛星「TESS」が2019年7月31日に、地球から31光年先に3つの系外惑星を発見しました。そのうちの一つは、生命が存在できる「ハビタブルゾーン」内にありました。
1-1 TESSが発見した系外惑星とは
系外惑星とは、太陽以外の星(恒星)のまわりを公転する惑星のことです。(※3)
太陽のまわりには、地球を含む8つの惑星が公転しています。公転とは周期的に周回運動をすることです。たとえば地球は太陽のまわりを1年(365日と6時間)かけて一周しています。(※4)
このように太陽系以外に系外惑星が存在することは、実はごく最近まで確認できていませんでした。初めて系外惑星が発見されたのは1992年のことです。続いて1995年にペガスス座51番星のまわりに惑星を発見し、2004年時点では120個の系外惑星が確認されています。(※5)
太陽系以外の系外惑星を探す理由は、惑星がどのように誕生したのかを解明するためと、地球上の生命は宇宙において特別な存在なのかという哲学的な問いの答えを出すためなどがあります。
惑星と呼ばれる天体の条件は、恒星のまわりを回っていること、質量が恒星よりも小さく自身の重力で周回できるほど大きいこと、そして同じ軌道上にほかの天体がないことの3点です。
そしてTESSが発見した3つの系外惑星は、うみへび座にあるM型わい星GJ357という恒星を周回しています。この恒星は太陽よりも40%低温で大きさと質量は3分の1ほどのものです。(※1)
そしてこの3つの系外惑星のうちの一つが、生命が存在する可能性のあるハビタブルゾーンにあることがわかりました。
1-2 3つの系外惑星を発見したTESSとは
ここであらたに3つの系外惑星を発見した、TESSについてご紹介します。
TESS(トランジット系外惑星探索衛星)は、系外惑星探査を目的とする宇宙望遠鏡です。地球を周回しながら、明るい恒星の周囲を回る惑星を探しています。
同じように系外惑星を探す人工衛星には、同じくNASAが2009年に打ち上げたケプラーがあります。このケプラーはすでに、稼働した9年間で2600個以上の系外惑星を発見しています。(※6)ケプラーは星空のほぼ一角のみを観測する仕組みでした。
しかしケプラーによって太陽系の外に多くの惑星があることが判明したことで、TESSは全天を対象に観測する仕組みになっています。4台のカメラを使い、全天の85%は網羅できるようになっています。
系外惑星を探す方法はトランジット法と呼ばれるもので、これは惑星が恒星の前を通過する時の光度の変化を利用して観測するというものです。
今回このTESSは地球から31光年先の系外惑星を発見しましたが、1光年は光が1年をかけて進む距離です。つまり今回発見された系外惑星は、31年前の姿ということになります。
2.発見された惑星の一つには生命が存在する可能性が

TESSが発見した系外惑星の一つはハビタブルゾーンに属することから、生命が存在する可能性があります。
2-1 なぜ生命が存在する可能性があるのか
TESSが発見した3つの系外惑星の一つ、GJ357dは、表面に液体の水が存在する可能性があります。
その理由は、このGJ357dが恒星から適度な距離を周回していることにより、ほどよい気温を保っているからです。この惑星が恒星から受け取るエネルギーは、太陽系の火星と同じくらいと見られています。
もしGJ357dが濃い大気を有しているならば、惑星を温めるのに十分な熱を閉じ込めることができるので、表面には液体が存在しうるということです。
もしGJ357dに液体の水があれば、生命が誕生している可能性があります。地球に生命が誕生したのは、海水に溶けていた数十の元素が結びつき、アミノ酸や糖となりタンパク質や核酸といった遺伝子の元になったからです。(※7)
同じようにGJ357dに液体の水が存在し、その中の元素が結びつくようなことがあれば、地球と同じように生命が誕生している可能性もあると考えられます。
2-2 発見された系外惑星の一つはハビタブルゾーンの中に
このGJ357dは地球の2倍近い大きさで、質量は6.1倍ほどになるとみられています。そして恒星のまわりを55.7日の周期で公転しています。
注目されているのは、恒星からの距離が太陽から火星までの距離とほぼ同じということです。この距離は、生命が誕生するのに適した範囲にあります。地球ももちろん、太陽からの距離はハビタブルゾーンの範囲内です。
ほかの二つの系外惑星ですが、まず一つめのGJ357bは恒星までの距離が太陽から水星の11分の1で平均気温は推計でセ氏約254度とみられています。そしてもう一つのGJ357cはGJ357bとGJ357dの間に存在し、質量は地球の約3.4倍で気温はセ氏約126度とみられます。
3.ハビタブルゾーンには生命が存在する可能性が

生命の存在が期待できるGJ357dですが、その理由はハビタブルゾーン内にあることと、液体の水が存在する可能性があるからです。
このハビタブルゾーンというのは、生命が存在できる領域のことです。その条件は、恒星から適度な距離にあることで惑星が適度な温度であり、気体の酸素が存在し液体の水が存在することです。太陽系の中では、ハビタブルゾーンは金星の外側から火星の内側までとなります。(※8)
ただし金星は太陽に近すぎるために照射が強すぎて、火星は逆に遠すぎるので太陽からの照射は弱すぎます。月も太陽からの距離は地球とほぼ同じですが、大気と水がありません。月にはもともと大気も水も存在していたことはわかっていますが、重力が地球の6分の1と小さいために宇宙空間へ逃げてしまったと考えられています。
TESSが発見したGJ357dの温度はセ氏マイナス53度ですが、もし大気が存在すれば実際の温度はもっと高いと考えられます。実際に大気が存在するかどうかは、今後の観測によって確認されることになります。2021年には大気観測ができる「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」が打ち上げられる予定ですが、これからの観測に期待が寄せられます。(※6、※9)
TESSによってハビタブルゾーン内に発見された系外惑星には、生命存在の可能性が期待できます。さらに詳しい調査のためには、実際に大気が存在するのかなど確認すべきことがまだまだあります。それも、これから打ち上げられる宇宙望遠鏡などによって観測されることが期待できるでしょう。
参照資料
※1 「地球から31光年先に惑星系を発見(Confirmation of Toasty TESS Planet Leads to Surprising Find of Promising World)」 NASA (2019/7/31)
※2 「NASA、系外惑星探査衛星「TESS」を打ち上げ」 AstroArts (2018/4/19)
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/9865_tess
※3 「太陽系外惑星とは?」日本天文協議会
https://tenkyo.net/exoplanets/wg/what_exoplanet.html
※4 「太陽系データノート2016」名古屋市科学館 (2017/11/4)
http://www.ncsm.city.nagoya.jp/study/astro/data/solar_system_data.html
※5 「太陽系外惑星探査:現状と展望」 東京大学大学院 須藤靖 (2004/3/28)
http://www-utap.phys.s.u-tokyo.ac.jp/~suto/myresearch/jps04_fukuoka.pdf
※6 「【解説】NASAの新衛星TESS、宇宙で何を?」 ナショナルジオグラフィック (2018/4/18)
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/041700174/?ST=m_news&P=2
※7 「どうして地球には生命が生まれたの?」 関西電力
https://www.kepco.co.jp/sp/energy_supply/energy/kids/science/topic11.html
※8 「ハビタブルゾーンってどこなの?」 日本科学協会
https://www.jss.or.jp/fukyu/cubicearth/glossary/07.html
※9 「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」 日本天文学会 (2019/9/11)
